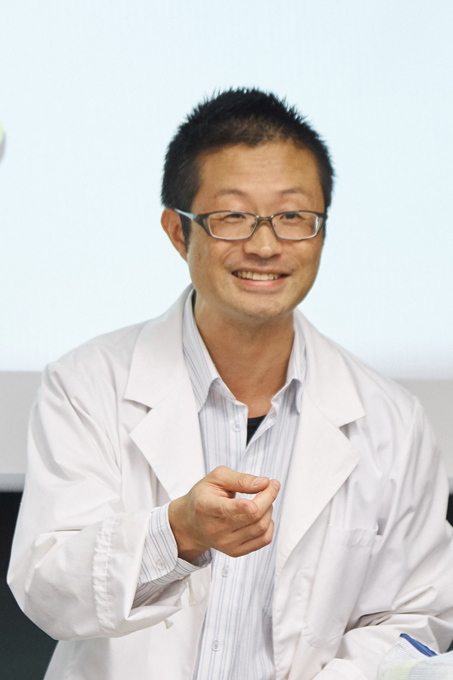小中学生時代の学力をピークにしない、学び方ARTICLE
西川 完途准教授 「なぜ教育に投資するのかを考えていく必要がある」
子どもの知的好奇心が衰えることはない
-
ダヴィンチマスターズ(以下、──)
生物多様性を学ぶためには、実際に自然と関わる必要があるのではないかと感じられます。先生から見て、今の低学年の子どもたちの「生きものと人との関わり」や「地球にいる生きもの」についての認識は、以前と比べて変化はあると思いますか? -
西川完途先生(以下、敬称略)
僕は、生き物としての人間の能力やスキルが数十年で変わることはないと思うんです。遊牧民やジャングルで暮らす子どもも、日本の都会で暮らす子どもも、一緒に遊んで同じことができると思いますし、知的好奇心に関してはどこの子どもほぼ変わりがないのではないでしょうか。
つまり子どもは昔も今も全然変わっておらず、変わったのは社会や大人。でも、子どもが大人になり、次の世代の子どもが現れるたびに社会は急激に変化していて、子どもだけは大人が失った関心を原始の状態で発揮している。大人はそれに自らの現在の社会感覚を押し付けようとする。
-
──なるほど、確かに子どもは道端のたんぽぽに気を取られたり、コンクリートを歩くアリを捕まえようとしたりしますね。
-
西川
子どもは生きものに強い関心があり、野外に出れば虫を捕まえたり、踏み潰して殺したり、木に登ったり、狩りの真似事を自然に好みます。本来遊びは厳しい自然で生き抜くために様々なことを学ぶためのきっかけのようなもので、それ自体が必要だからするわけではありません。大人が趣味でするスポーツにしても音楽にしても、生きるためには必要はありませんよね。人間には本能として遊びたいという気持ちが備わっていて、それはもともと自然の中で学ぶために重要だったはずなのです。人間も野生の生き物だったのですから。
それが人間の中に残っているから、子どもの知的好奇心が急に衰えるなんてありえないですし、いつでも子どもは動物好きだったり自然好きだったりするのではないかなと思います。逆にそこを伸ばすことで、人間の潜在能力が将来大きく発揮されるのではと信じています。不要だったら進化の過程で消えているはず。
-
──ただ都市部の子どもたちは、土に触ることを敬遠したり、虫を怖がったりする傾向があります。これは触れる機会が減っているからかと思いますが、直せるものでしょうか。
-
西川
僕は、幼い頃の環境によって子どもは違う反応を見せると思います。「子どもが敬遠する」という場合、まずは親自身が変わるといいですよね。近年の傾向として、お父さんが自然の中で遊ぶこと、特に虫を捕まえることが苦手というケースが増え、自由研究の時期になると困り果てたお母さんから質問が来ることがあります。お母さんによっては、子どもを連れて研究室訪問にまで来られるのですが、お父さんにもぜひ変わってほしい。「セミなんて触れない」というお父さんはまず、子どもと一緒に観察から始めてみるといいと思います。一緒に釣りをして、釣った魚を食べるのでも良いでしょう。
ただ低学年のうちに自然に触れる機会を増やしていくのはとても良いことなのですが、論理的に学べるようになる小学校4年生以降という、一番大事な時期に触れる機会がなくなるようでは、非常にもったいないと思ってもいます。
自然を学ぶには優秀な先生が不可欠だが
-
──4年生以降だからこそ学べることがあるということですか?
-
西川
例えば同じ両生類の解剖でも、低学年に対しては、動物を解剖すると血が流れるのを見せて、自分たちにも同じ血が全身を流れているのだよと教えますが、中〜高学年に対しては「血はどういう仕組みで流れているのか」「なぜ逆流しないのか」「どうして赤いのか」「血が赤くない動物もいるのか」という問いかけをしてあげて、考えさせることができます。生物学だけではなく、物理学や化学の話も関わってきて、そこから教えられることは多いのですが、一方で中学受験に進むために、覚えることが格段に増えてきて、かつ自然や実物に触れ合う機会が激減しますよね。
休みの日にちょっと自然に触れようとしても、都会にはその場所がありません。私の住んでいる京都なら車を30分も走らせたら登山ができ、生き物がいる環境がありますが、関東は平野が広く、山が少ないので、自然に近い遊びをしようとすると1時間半かかるというエリアの方も多いのでは?
だからこそ、東京で「セミの声を聞こう」などの自然体験イベントを開くと、あっという間に何百人もの人が集まるわけで、それは本来、残念な話だと思います。
-
──理想としては、自ら生物多様性に興味を持つ子どもに育てることですが、そのためには本物の自然がないと叶わないものでしょうか。作られた自然のなかでの観察や体験には意味はないでしょうか。
-
西川
作られたものでも教え方はあります。例えば公園の植栽や街路樹も、庭師さん達が植物の生態的特性などを考えて種や組み合わせを選んで植えています。また、例えば日本の希少種は殺したり解剖したりはできませんが、外来種として日本に入ってきて駆除されている種であれば解剖をする機会を持つことも可能です。
今の都会にいる生物の多くは外来種で、私が解剖実習に用いているウシガエルもそうです。それらを駆除するテレビ番組の企画も出てきています。どうして外来種が増えているのか、逆に増えなかった外来種もあるはずでは、日本から外国に行って外来種になっている種は何か?などなど、これだけでも生物多様性やその保全について重要なことを学べるわけですが、時間的に、または能力的に教えられる先生がいるかどうかなんですね。
近年は先生にとって厳しい時代が続いており、特に初等教育は労働量の多さと待遇が見合っていません。ヨーロッパなどでは、博士号を取った人が小学校の先生になり、高い報酬を得ているようです。そうした先生たちは研究の経験があるので、語学も堪能で、プレゼンもうまく、子どもの好奇心にも創造性を持って応えることができます。様々な国の研究者ともつきあってきているので、世界情勢にも明るいわけです。国の高等教育の成果としての虎の子の人材ですが、今は子どもが減ったことで就職難になり彼らを活用できていません。
優秀な先生が経済的にも好待遇で雇用され、教材を用意し、かつ、放課後の子どもたちの面倒は見ることはなく、授業が終われば帰るという無駄な負担のない環境があるからこそ、余裕を持っていい教育ができるのでは。
翻って日本の先生は今、心を病むほどに忙しい。優秀な人材に対し国が高給を出して雇わなければ、現状は解消されないでしょう。

第18回ダヴィンチマスターズでの西川完途准教授のプログラム「両生類の解剖と生物多様性について」より
なぜ教育に投資するのかを考えていく必要性
-
──では、生物多様性の重要性について親はどのように子どもたちに日々、伝えていけばよいでしょうか。
-
西川
学校が、先生が教えてくれて当然という考えもあるかもしれませんが、実際は子どもに一番教える機会があるのは親御さんだと思います。できないなら、そのチャンスを作るのも学校の先生ではなく親御さんではないかと思います。自然がない場所で何をするかとなると各家庭では難しいとは思います。色々な経験をしたことで教職を離れている先生も多いので、逆にチャンスと思って、例えばPTAで学校の代わりに専門家や地元の自然や歴史に詳しい年配の方を呼んで、授業をしてもらうということも考えられるでしょう。もっと、親御さんが積極的に提案をして、出資してもいいのではないかと思うのです。
京都にはもともと「番組小学校」という、明治維新後の1869年に、当時の京都の住民自治組織であった「番組」を単位にして、市民が投資して創設した64の小学校があったのですが、その経営をするために京都市では銀行まで作ったそうです。「これからは教育だ」と判断したからでしょう。
自分たちで教えるのが難しいと感じるのであれば、保護者の皆さんが考えて学校や地域に呼び掛け、講演会や授業の実施をすることは可能なのではないでしょうか。その時には、お父さんやお母さんにも授業を受けてほしいですね。
-
──なるほど。自分たちで講演会を企画するという手立てもあるのですね。
-
西川
生物多様性に関していえば、この数年で環境金融という概念や政策が生まれていて、生物多様性保全に取り組んでいる企業や国に優遇した金利で貸し付けたり投資をしたりする動きが出てきています。ヨーロッパはこの環境金融で世界を牽引しようとしていて、お父さんお母さんのお勤めの会社も影響を受ける可能性が出てきているので、実は他人事ではありません。題材は何でもいいのです。最も身近なのは、食べている物でしょう。スーパーに並ぶすべてのものは、多様性に関わるものですから講義の材料になります。日本は自然環境が多様で豊かなので、生物多様性に関する教育には、とても向いている国なのです。ただ、家で話をしてもいいのですが、専門的な話をするとなると、ネットなどで手軽に検索できる時代になったとは言え、やはり専門家が必要になります。家庭でできない部分を教員や専門家が担当するのが本来の形ですよね。
-
──具体的にどのような先生をお招きするといいのでしょう。
-
西川
大学でもしっかり勉強して、大学院でも研究してきている若い先生がいいのではと個人的には思っています。ボランティアではなく先生に報酬が出るようになれば、継続していくことも可能でしょう。研究ばかりしている先生も社会経験が少ないと色々と問題なので、win-winの関係になれるのではと思います。教育は投資です。ある意味、将来の納税者を育てて国に還元されると思えば、国がもっと投資すべきところでもあります。無償にこだわりすぎると、ボランティアで疲弊する人たちが出てきてしまいます。
改めて、学校に過度な期待をすることなく、なぜ教育に投資するのかを考えていく必要があるかもしれませんね。
小中学生時代の学力をピークにしない
-
──ちなみに先生ご自身は、どのようにして今の研究テーマ(両生類の系統分類、生物地理、自然史的研究)にご興味を持たれるようになられたのでしょうか。
-
西川
僕はもともと福岡の田舎で育ち、魚の研究などがしたくて京大に憧れて受験をしましたが第一希望の理学部は学力が足りず、諦めて農学部に入りました。しかも農林経済学科というところで生物との関係は薄いですが、むしろ今は当時の勉強が役に立っています。その時に一般教養の科目でカエルの授業をされている先生がいらして、両生類、とくにサンショウウオの仲間が面白いと思うようになり、大学院は今の職場の研究科に入りました。一旦は教員を目指したのですが、研究が面白くなり、紆余曲折を経てそのまま続けています。色んな面白い先生や、世界レベルの研究者、破天荒な先輩が京大に集まっていたことがあり、そうした出会いがあってのことですね。高校時代には全く想像できなかったことであり、しんどくても勉強して大学に入ったからこそ体験できたと思っています。なので、入学してくる子たちのため、その伝統を維持したいなという意識があります。
-
──研究職に就くためには、ずっと「何か」を好きでい続けないとだめなのかと思っていました。
-
西川
必ずしもそうではありませんし、むしろ思い入れが強すぎると研究に対して不器用になってしまうこともありますね。先ほどお話ししたように、私も実は全然思ったように歩んできていなくて、大学や大学院受験で悩んでいる人には、あまり考え過ぎても仕方ないのでは、と根も葉もないことをよく言って嫌がられます。ハーバード大学など、アメリカの大学に多いのですが、日本でも国際キリスト教大学など「リベラルアーツ教育」を展開する大学が増えてきています。僕のいる総合人間学部でも文系、理系は一応ありますが、どちらでもない美術をやる子もいます。ただし、そもそも日本の大学も以前は教養教育が盛んでした。
近年は学際教育が流行していますが、米国では大学院くらいから専門的な勉強をするんですね。それまではいろんな勉強をしますし、ヨーロッパもそういう傾向がありますよね。フランスなどは大学入試で必ず哲学の論文試験があるとか。
とはいえ、今の日本やシンガポールのやり方を否定するものではありません。現状で、日本の小中学生の学力はかなり高いことは事実ですよね。それを人生のピークにするのではなく、その先につなげていくのが今後の課題でしょう。
-
──興味を持って発見して研究するというのは、すごいことに思えます。でもそれを当たり前にするために、できることはありますか?
-
西川
それこそ、ダヴィンチマスターズのような体験型のイベントを拡大できるように、親がコミットしていくことではないでしょうか。学校にこういうことを取り入れてほしいと入っていくこと。それが子どもたちを刺激しますし、親御さん自身の学びにもつながるのではないでしょうか。最近は還暦を過ぎた方が大学院にも入学して来られます。親御さんも学生になっても良いのではないですか?